藻類35億年の力をひらめきのイノベーションで引き出す場所
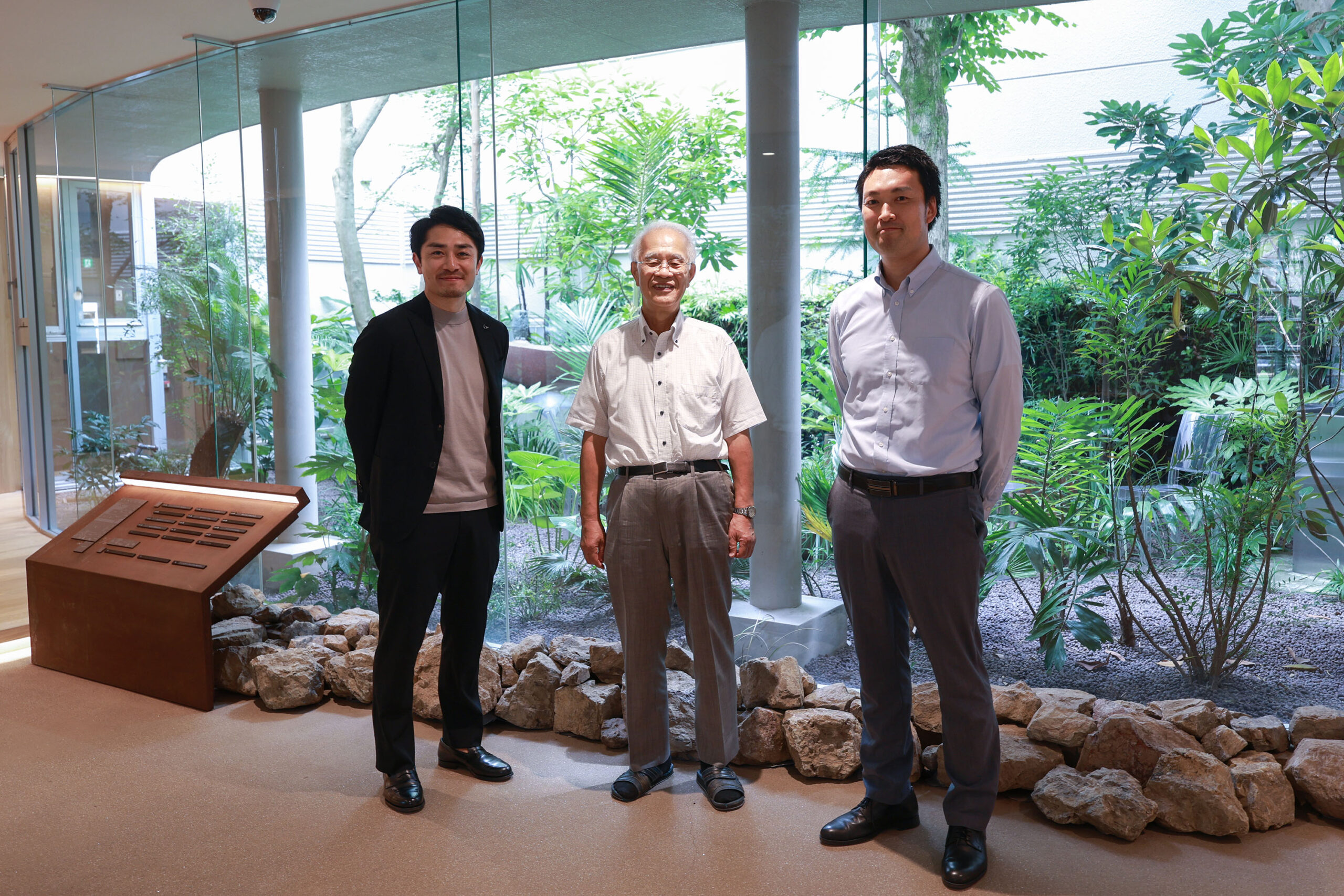
オリエンタル技研工業株式会社 執行役員/経営戦略室長柄澤 建之介(からさわ けんのすけ)
大学卒業後、オリエンタル技研工業株式会社に入社。国際業務部にて、欧米の先進的な研究設備の日本市場への導入とマーケティング戦略を担当。2020年より現職。コーポレートブランディングを軸に、新規事業開発に取り組んでいる。研究施設やイノベーション環境構築のノウハウを活かし、ディープテック領域の成長支援を目的としたインキュベーション施設の企画をリード。2024年4月、つくば市に「XiS Worksite」をオープンし、研究者やスタートアップとともに、“ひらめきの瞬間”を生み出す場づくりに挑んでいる。
フィコケミー株式会社 代表取締役CEO渡邉 信(わたなべ まこと)
大学院理学研究科で理学博士取得後、国立環境研究所生物環境領域長、内閣府総合科学技術会議参事官(環境・エネルギー担当)、筑波大学大学院生命環境科学研究科教授、国際藻類学会長、日本微生物資源学会長などを歴任。研究所勤務当時は、自然環境保全に係る研究していたが、未来を作る研究に取り組もうと、藻類から有用成分を生産する研究をスタート。2023年フィコケミー株式会社を設立。誰もが心身ともに健康で充実した暮らしができる持続可能で平和な社会の実現に向け、研究開発や国内外の連携に力を注いでいる。
つくば市 スタートアップ推進室 室長屋代 知行(やしろ ともゆき)
つくば市出身。大学卒業後、民間研究部門を経て2006年につくば市役所へ入庁。途中、経済産業省への2年間を経て、政策企画、防災、シティプロモーション、現市長直下の政策マネジメントに従事し、スタートアップ支援7年目に突入中。第1期プラチナ構想スクール修了、NEDO-SSA Associate(4期)、TXアントレプレナーパートナーズ メンター会員(個人として副業活動)、インパクト・コンソーシアム官民連携分科会(所管:経産省)コアメンバー。
聞き手:つくば市 スタートアップ推進室室長 屋代知行
※本インタビューでは、スタートアップとベンチャーを同義語として扱います
筑波研究学園都市から生まれる多くの研究成果は「ディープテック」と呼ばれ、そのポテンシャルは世界中から注目を集めています。一方で、研究者自身が学術界から産業界へと向かう道程(スタートアップ/ベンチャー)は、スピード感や文化面などで大きな違いがあり、とても険しいものと聞きます。そこを乗り越えるためには、ハード/ソフト両面での産業界のサポートが欠かせません。
今回は、1978年からつくばに拠点を置いてラボ設備や研究環境をプロデュースしているオリエンタル技研工業株式会社の柄澤さんとそのオリエンタル技研工業が自社施設で運営するイノベーション拠点「XiS Worksite」に入居するフィコケミー株式会社の渡邉さんをお迎えして、ディープテック・スタートアップを支援することへの挑戦と研究学園都市「TSUKUBA」のスタートアップ・エコシステムへの期待についてお話しします。
01. サイエンスを当たり前の文化に
屋代
柄澤
よろしくお願いします。
渡邉
よろしくお願いします。
屋代
渡邉さんとは、リアルでの対面は実は初めてなんですよ!これまではオンラインで何回か意見交換をさせていただいていましたが、お会いできることがどれほど待ち遠しかったことか!
渡邉
こちらこそ、リアルでの対面が実現できて嬉しく思っております。本日、私からは、新規技術を社会に実装するために2008年から作ったいくつかのスタートアップ会社に関与した経験をもとに、話させていただきます。実は亡くなった両親からは企業経営は私の性格には絶対合わないので、生物の研究だけを楽しんでいなさいという遺言をもらっていましたが、2015年にどうしてもスタートアップ企業の経営を行わなければならない状況に直面してしまい、両親の遺言を破ることになりました。それでも経営に入ったからには最後まで真面目に頑張ってやると決心し、進めてまいりました。失敗と成功の繰り返しでしたが、不思議なことに意欲が萎えることもなく、現在に至っております。その間の経験をもとに話すこととなりますので、一般的に言われていることとは違った変な意見で皆様の気分を害することがあるかもしれませんが、その場合はご容赦ください。
屋代
いえいえ、人もスタートアップも個性があってこそ、正解がない時代ですから失敗と成功の繰り返しで生まれる道こそがすごく大切だと実感しています。そのようなお話が聞けると知っただけでワクワクしています!
そして、柄澤さんとはここXiS Worksiteができる前からのお付き合いですね。こうやって完成して、渡邉さんのフィコケミーが入居しているところを見ると感慨深くて涙が出てきそうです。
柄澤
屋代さんにはXiS Worksite の企画段階から色々とご協力いただき、2024年4月にこの施設をオープンすることができました。この場をお借りしてご協力いただきました関係の皆さまに改めてお礼を申上げます。
屋代
おお、少し硬いですね(笑)、後ほどXiS Worksiteについてお聞きしたいと思います。

屋代
さて、今回つくばのスタートアップ・エコシステムのオウンドメディアである「Tsukuba Startup Journey(以下「Journey」)」のインタビュー記事に出ていただきありがとうございます。このJourneyでは、つくばのアカデミアから生まれるディープテック・スタートアップとそれを支援する者を旅の仲間と形容して紹介しているインタビュー記事に加え、つくばエリアのスタートアップに関する実績や各支援機関の支援情報、活動するスタートアップの紹介などをしています。まだコンテンツは作成中ですが、このようなインタビュー記事を先行して公開していまして、その中で、私がどうしてもお話を聞きたかったのが、柄澤さんと渡邉さんです。お二人とも私が深く関わったという贔屓目はありますが(笑)、それを抜いてもつくばのスタートアップ・エコシステムを代表するひとつの支援モデルになると感じています。まずはXiS Worksiteについてからお話しを伺おうと思います。
実はですね、オリエンタル技研工業さんがXiS Worksiteの構想を掲げていると知ったのは偶然なんですよ。とある参加者限定のオンラインイベントがありまして、そこでは筑波大学国際睡眠医科学研究機構(以下、IIIS)の柳沢正史機構長が講演されたのですが、私は純粋に柳沢先生のお話をお聞きしたくて参加していました。オリエンタル技研工業さんはIIIS研究棟のデザインや設計を担当されていたご縁で出ていたと聞いています。そのときに、スタートアップや企業向けのラボ付きオフィスの話題になった際に、モデレーターの方がオリエンタル技研工業さんに無茶振りしたんですよ(笑)。聴講者に振るってすごいな~って思いながら見てたんですが、「つくばのショールームをリノベーションしてオープンイノベーション、インキュベーション施設にする構想がある」と発言されたんですね。そのとき私は「これだ!」と閃いてZoomチャットで参加されていた担当の方にメッセージを送ったんです。実は、当時はつくば市内には民間のラボ付きオフィスが少なく、株式会社つくば研究支援センターさんも持っているのですが、当時は満室に近かった。アステラス製薬さんのSakuLab-Tsukubaもまだ始まっていなかった。だから、私もこの課題はずっと認識していて、でも箱物を市が直接やるのは難儀だな~と思っていた矢先の出会いでした。それが私とオリエンタル技研工業さんの最初の接点ですね。
柄澤
そうでした!私たちオリエンタル技研工業は1978年の創業以来、ずっとつくばにはお世話になっていました。ショールームを東京本社に移転するという計画が決まり、今後この施設をどのように活用するか検討している中で、「研究環境づくりで培ってきたこれまでのノウハウやネットワークを活かして、これまでと違った形でサイエンスコミュニティや技術革新的に貢献できないか」と模索していたのが、XiS Worksiteのきっかけです。屋代さんが聴講されたイベントのタイミングでは、インキュベーション施設にするというのはまだアイデアの1つといった段階でしたが、その無茶振りがきっかけになり、「言っちゃったからには、やるしかない」的な感じで本格始動したというのが本当のところです(笑)。
屋代
有言実行とはまさにこれ!でも担当者にとってはモヤモヤしていた状況で、こういった外部の方々がいる場で発言することが、一歩を踏み出すきっかけになるんですよね。もちろん勇気と責任が求められると思いますが、それを出来ちゃうのがオリエンタル技研工業さんの素敵な社風なんじゃないかなと感じましたし、イノベーションに必要な空気感だと思います!
では、そのXiS Worksiteについて簡単にご紹介ください。
柄澤
XiS Worksiteは、1988年に工場として稼働していた施設をフルリノベーションし、ディープテック・スタートアップ向けのインキュベーション施設として2024年4月にオープンしました。
オリエンタル技研工業はいわゆるウエットラボで使用されるドラフトチャンバーや実験台といった設備の開発・製造を主な事業とし1978年に発足し、研究施設/イノベーションセンター専門の建築設計事務所であるグループ会社「プラナス株式会社」とともに、主に医薬、化学、食品、化粧品などのメーカーさまの研究施設を総合的にプロデュースしてきました。最近ではレンタルラボが増えてきていますが、不動産屋さんやデベロッパーさんが運営しているものがほとんどです。「研究施設やイノベーション環境の構築を専門に行う私たちがやるインキュベーションセンターとは」といった点、つくば市さんやスタートアップの方々にもニーズや課題のヒアリングなどを行い、「手ぶらでScience、ときどきBBQ」というコンセプトを軸に施設計画を行いました。国内では珍しい「セットアップラボ」というのが他の施設との大きな違いになります。スタートアップの方々にお話を伺ったところ、皆さん口を揃えて「ラボを整備する初期投資のハードルがすごく高い」と仰っていました。そこで私たち自身が研究設備メーカーであるという特徴を活かし、すべての部屋に実験台や流し台といった基本的な設備が備わった「手ぶら」に近い感覚で新たなイノベーションに挑戦できる環境の整備を行いました。また、さまざまなプレイヤーの交わりからオープンイノベーションを加速化するための仕掛けとして、BBQテラスを設けました。BBQは強力なコミュニケーションツールです。BBQイベントで交わり、距離を縮めることで、すでにXiS Worksiteに入居するテナント同士や外部の組織とのコラボレーションが生まれています。
屋代
ありがとうございます。オープニングイベントに五十嵐市長とともに招待されたのですが、私の率直な感想は「何だこりゃ!?」でした(笑)。つまり、先入観というか、「インキュベーション施設とはこういうものだ」というイメージがあったので。でもBBQ会場や某ロックバンドの曲名をコンセプトにした会議室などの設備、リラックスできる香り、それでいて本格的な実験ができるラボを見たときに、「研究開発施設じゃないみたいで楽しい!」という感覚に変わりました。
これって、以前林社長がインタビュー記事で「科学というのは理系の、ある種特別なマニアックなイメージがあって、それをもっとカジュアルで格好良くて誰もがサイエンティストであるという日本の文化を作っていこうということを、ここで目指しています。というのは、海外では、innovation for everyoneとか言いますが、ヘビメタをやってるんだけどもサイエンスも好きというような人がいっぱいいたりとか。サイエンスというのは、特別なものでなくて、誰でもやれるんだと、そういう文化づくりをしていこうと思っています。」とお話しされていたことですよね。
スタートアップが社会実装していくためには、当然、社会側のテクノロジーに対する理解度というか許容度が高くないと難しいなとも思っています。そのため、サイエンスを身近にしていくという社会への貢献をも図っていることは、行政としても嬉しいですね。
柄澤
私たちはずっと“科学”という言葉を真面目に捉えすぎていたのかもしれません。でも、サイエンスってもっと自由で、もっと楽しくていい。
「研究者=アカデミックな人」というイメージを壊したい。サイエンスを“誰にとっても使えるツール”にするには、まず研究の現場が変わるべきだと思ったんです。だからXiSでは、香りの演出も、音楽の名前がついた会議室も、本気で取り入れました。“働く場”ではなく、“発想が育つ場”として、ここをスタートアップのみなさんに開放したい。そういう想いでつくりました。

屋代
とはいえ、やはりそこはオリエンタル技研工業さんなので、本格的なラボ設備です。これはスタートアップにとっても有難いです。この施設は確か経済産業省の事業に採択されているんですよね?
柄澤
はい。ちょうど施設の計画を進めているタイミングで、偶然経産省さんから「地域の中核大学等のインキュベーション・産学融合拠点の整備事業」をご紹介いただき、応募させていただきました。この補助により当初の計画よりも充実した環境整備、特に入居者さんが共用で使用できる共通機器の拡充を実現することができました。こうやって振り返ってみると、色々な出会いや偶然がドライブとなって今に至るんだな、と。
屋代
この事業の目的が「ディープテック・スタートアップの持続的な成長を支える施設の充実を図る」とあるので、まさにつくばにぴったりな事業ですね!そしてそれに採択されたことは、我々も嬉しいですし、とても期待しています。
でも、先ほどの偶然の出会いのときも感じたのですが、オリエンタル技研工業さん自体はスタートアップ支援をやっているわけではないので、インキュベーション施設を作るとしても、単なる部屋貸しに終わってしまうんじゃないかと心配していました。もちろん、市内では供給不足なのでそれでも嬉しいのは間違いないのですが、そのあたりの考えというか、入居者を成長させるための仕組みについて、何か対策はあったのでしょうか?
柄澤
私たちはスタートアップ支援の専門家ではありません。でも、自分たちが持っているアセットを使えば、本気でスタートアップの背中を押せると信じています。
これまでに築いてきた業界ネットワークやクライアント基盤を活かし、入居企業と大手企業との接点をつくる。ここから事業提携が生まれれば、単なる施設提供ではない、本質的なインキュベーションになると思うんです。
屋代
なるほど、研究施設の設計や建築に強いオリエンタル技研工業さんならではの強みですね!ディープテック・スタートアップの取引先は一般ユーザーではなくメーカーなどの民間企業であることが多いので、そういったつながりを持っていることは何よりの支援ですね!
02. 基礎研究から開発研究(事業化)、そして社会実装とスケール化へ向けて
屋代
さて、いよいよ渡邉さんにお話しを伺おうと思います。まずは渡邉さんが立ち上げたフィコケミー社の概要を紹介してください。
渡邉
フィコケミー社を立ち上げたのは、2つの理由がありました。一つ目は、藻類のスーパー機能性成分であるフコキサンチンを高含量で産生する珪藻シリンドロテカの大量培養技術を開発し、フコキサンチンを大量に生産して、グローバルなビジネスを展開すること、二つ目はボトリオコッセンの機能性評価研究を実施し、機能を明確にしたうえで、その化粧品事業を本格的に発展させることでした。
国際的視野でフコキサンチンの機能・効能についての研究をみますと、この10年で飛躍的に進み、多数の論文が発表されています。これまで判明した機能・効能は、抗肥満、抗糖尿病、抗酸化、抗腫瘍、抗炎症、脳・心血管保護の他にも、抗線維、抗結核、腎臓保護、肝臓保護、抗メラニン活性、抗菌活性、抗マラリア、神経保護、腸内微生物相調節・改善など多くの機能・効能をもつことがわかってきました。まさに他の機能性成分とは違って多くの機能が認められるスーパー機能性成分といえるものです。フコキサンチンは化学合成ができず、もっぱら褐藻類のコンブの仲間から抽出されたものが市場に提供されています。しかし、コンブのフコキサンチンの含量は少ないため、市場では純粋のフコキサンチンはkg当たり400万円~800万円という非常に高い値段で販売されています。私たちの基礎研究により、フコキサンチンを大量に産生する珪藻シリンドロテカを発見・改良したことで、低コストでの生産が可能となりました。XiS Worksiteに移ってからは、珪藻シリンドロテカの大量培養技術とフコキサンチンの大量生産技術を確立したことから、グローバルなビジネス展開ができるようになりました。
ボトリオコッセンについては、筑波大学にいたときから、(株)デンソー様と共同研究を実施し、デンソーのボトリオコッセンを含む化粧品「モイーナ」の開発をサポートしてきました。モイーナの評判はよかったのですが、開発者の定年退職が間近になったときに、デンソーからフィコケミーの前身企業であるMoBiolテクノロジーズに化粧品事業が譲渡され、さらにMoBiolテクノロジーズの解散にともないフィコケミーに譲渡されました。ただしボトリオコッセンの機能については、保湿効果以外は不明であり、ビジネスでの限界を感じていたことから、機能評価の研究を進め、XiS Worksiteに移った時点で皮膚の抗老化機能をもつことが明確になりました。
フコキサンチンを産生するシリンドロテカとボトリオコッセンの抗老化機能は、2023年夏に特許出願後1年となる2024年8月に特許として認定・登記されています。

屋代
ありがとうございます。ものすごく動きが多様ですね!一般的なディープテック・スタートアップへのイメージですと、ここまで事業を転回していくことは見かけません。
ちょっと話を過去に戻しますが、私が渡邉さんを知ったきっかけですが、2010年に当時の政府が「国際戦略総合特区」制度を構築していました。これにつくばエリアで申請しようと機運が高まり、当時の私は市役所での特命担当として今で言うパブリックアフェアーズのようなロビーイング活動で霞が関や永田町を回ってました。そのとき、つくば側として根幹となるプロジェクトを洗い出していたときに、藻類バイオマスエネルギーの実用化として渡邉さんの研究を初めて確認しました。端的に言えば、石油の代替燃料として藻からオイル(バイオマス)を生産するというものです。すごい技術が出てきたな~と感心していたら、何と2011年11月のゴルゴ13第517話「ミクロの油田」で渡邉さんがモデルと思われる人物が出てきてビックリしました(笑)。それはさておき、インターナショナルな小説とも言われる漫画で取り上げられるのですから、世界中で関心が高いと想像できました。
さて、現在のフィコケミー社の事業では石油代替燃料ではなく、先ほどのお話のとおり健康食品と化粧品という事業モデルですが、藻類はひとつの種類が多様な機能を持ち合わせているのでしょうか?それとも世の中には多くの藻類が存在してそれぞれに機能があるのでしょうか?藻類について少し簡単に教えてください。
渡邉
藻類の特徴を述べる前に、フィコケミーは、NEDOのバイオものづくり事業からの補助金を得て、ANAホールディングス様と共同で藻類バイオマスネルギー技術実証研究を実施していること、さらに国土交通省の補助金で実施した下水資源で培養した土着藻類からのバイオ原油生産事業もフィコケミーが継承していることをお伝えしておきます。特に後者の事業はつくば国際戦略総合特区と国交省のプロジェクトで大きな成果をあげています。
藻類は35億年前に地球上に出現した最初の光合成生物であり、当時地球の大気の主要成分であるCO2を固定して、酸素を発生することで、地球環境を革命的に変化させたものです。発生した酸素により水中の金属が酸化され、それにより鉄は鉄鉱石となりました。人類の鉄文明の基礎は藻類が作ったものと言えます。さらにCO2の固定・酸素の発生が進み、オゾン層の形成により生物が陸上に侵出して、多様な環境のなかで多様な生物が進化してきました。陸上植物が現れる1億年前には現在の大気が形成されました。藻類はエネルギー形成にもかかわっています。現在石油生産国である中東は、一億年前は存在しておらずテーチツ海という浅海でありました。そこに藻類プランクトンがそれを捕食する動物プランクトンとともに大発生し、それらが海底に沈殿したものが高熱と高圧により石油に変性したとされています。
藻類は光合成で発生する活性酸素を防御する多種多様な成分を作り上げております。人体内で発生する活性酸素は人間の疾病の85%に関与していると言われていますので、人間の健康の維持、回復等に役立つ成分を多数持っている生物といえます。
屋代
なるほど!さすがは35億年の力ですね!食品などでもミドリムシを使ったものがすでにスーパーやドラッグストアで買える時代ですからね。
ところでフィコケミー社の藻類とビジネスモデルですが、順番と言いますか、化粧品や健康食品を大きなマーケットとして狙った上で、その機能を持った藻類を研究で見つけ出すのか、いろんな藻類を研究した上でそれらが一番生かせそうな事業へと進んでいくのか、このあたりを教えてください。
渡邉
フコキサンチンやボトリオコッセン事業のように、新しい機能を持った藻類及び成分の開発がフィコケミーの機能性成分事業の中核となっております。フィコケミーは、すでに国際的に実用化されている藻類成分を国内で事業展開するという二番煎じのビジネス戦略をもたず、材料や生産過程に新規性・独自性・優位性をもった事業を実施します。また、藻類エネルギー開発においては日本のような国土が狭く、四季折々に気候が変動する国で、未利用資源や廃棄物資源を活用して、狭い面積で藻類エネルギーを大量に安定的に、低コストで生産するという世界でも類をみない技術開発を実施しています。
屋代
ありがとうございます。藻類という35億年の歴史と日本という地勢的特徴が強みを生かしての事業展開は、まさに強みそのものですね!
ちょっと気になったところがありまして、フィコケミー社は事業会社であってアカデミアではありません。つまり、一般論的に、ある程度の産業化を見据えていなければお金も支援も集まらないと思っています。事業としての社会実装やスケール化(量産化)を中長期的な視点に入れる上で、現在、フィコケミー社がこのXiS Worksiteに入居されていることはプラス要素としてあると先ほど仰っていましたが、そこは入居検討においてはポイントなのでしょうか?
渡邉
ご懸念はよく理解できます。米国にいる友人からも技術を中核とする企業が成功する例は米国では5%程度と言われております。事実、事業継続が困難になったことも幾度か経験はしています。にもかかわらず、新しい科学で社会イノベーションをもたらしたいという信念を捨てることはできません。幸運なことは、今度はダメかと思うような危機においてもなぜかそれを救う状況がうまれてくることです。XiS Worksiteに入居以降も、小規模ながら同様な危機が起こっていますが、オリエンタル技研工業様の理解やサポートもあって、ANAホールディングス様等のようなフィコケミーの技術を高く評価し、かつ信念を理解した複数のパートナーを国内外で得ることができております。あとでやや詳しく話しますが、XiS Worksiteに入居のプラス要素が先天的にあったわけではなく、私たちの条件に合うところがここしかなかったことが入居した理由でした。しかし、入居後のフィコケミー事業の発展は想定を超えています。
屋代
なるほど。確かに、成長するスタートアップは何よりも事業拡張を見据えた場所探しが一番大変だとも聞きます。物件探しと出会いは運任せのような感じがします。これはオリエンタル技研工業さんとしてもXiS Worksiteを立ち上げた成果として、うれしい出会いですね!
柄澤
本当にその通りです。フィコケミーさんのような素晴らしい企業に入っていただけて、本当に光栄です。1年たって、正直「もっとできたな」という反省もあります。でも、今いろいろ仕込みを進めています。これからは新しい関係を築いていければと思っています。渡邉代表、引き続きよろしくお願いいたします!

03. イノベーション創出を支えるための新機軸
屋代
ところで、渡邉さんは筑波大学の生命環境科学研究科で藻類バイオマスをはじめとした研究をされて来られました。実は、このJourney5月号では筑波大学の国際産学連携本部と一緒に「学際性」をテーマにお話ししました。筑波大学は、つくばのスタートアップ・エコシステムにおいてとても重要な組織であり、アントレプレナー育成を中心に国研や民間企業を引っ張っていく存在です。その学際性という言葉は私はとても重要だと考えています。私は、イノベーションというものはまったく新しいものを作り出すのではなく、世の中のあらゆるものを新しく組み合わせて、新しい価値を提供していくことだと解釈しています。それは学際性そのものです。フィコケミー社のビジネスモデルも藻類単体ではイノベーションは起きないと思いますし、イノベーションを構成する要素の一つだと思います。その際、藻類と何を組み合わせればイノベーションの芽となるのか。これはもう学際性のように多くの民間企業や支援機関がどんどん関わってくる必要があるんじゃないかと考えます。フィコケミー社を経営する上で、このあたりの考えをお聞かせください。
渡邉
学際性の重要性・必要性は基本的には理解できます。ただし、あくまでも学術分野でのみ成立する概念であると私は考えております。大学は基本的には研究者個人の能力に基づく研究開発・教育を行っていますので、個人の自由な発想による研究が基本です。分野横断的な総合的なプロジェクトを推進するときに学際性が必要とされることはあります。しかし、数多くの総合的プロジェクトのリーダーを務めた経験から申し上げますと、企業のプロジェクトと比べて目的が発散的であり、寄せ集め的あるいは同床異夢的なところがあり、まとめるのにかなり苦労しました。個別技術であっても社会に実装することを真剣に目指すのであれば、必然的に他の分野と統合せざるを得ないのですが、個別技術が寄せ集めである場合は、最後までバラバラで、プロジェクト終了後は雲散霧消してしまいます。
個別技術の社会実装について、フコキサンチン事業開発・発展を例にしますと、フコキサンチンを高濃度に蓄積する珪藻の開発と培養技術の最適化及びフコキサンチンの機能・効能評価の動物試験は個別技術レベルにありますが、社会実装を本気で実現するとなると、1)機能・効能をヒトに適用するために必要な安全性試験を倫理委員会の承認をえて実施(臨床試験)、2)培養の個別技術の知見をもとに大量生産プラントの設計に係るエンジアリング技術、3)プラント建設・設置に係る商用プラントシステム建設にかかわる関連法や社会規範・社会道徳、ステークホルダーの利益・要請等コンプライアンスを遵守する施設建設・設置の条件設定(コンプライエンス科学)、適切なビジネス戦略に基づくマーケティングの推進(ビジネス科学)、会社の適切な経営(経営学)等、必然的に学際的になってしまいます。したがって製造業では、確かな個別技術にもとづく学際的技術・システムが凝縮していると考えていただければよろしいかと思います。学際性という言葉に新鮮さや重要性を感じられることを否定はしませんが、企業では当たり前のこととして実行されていることを、私は身をもって体験し、認識を強くしております。
屋代
ありがとうございます。これはもうアカデミアと産業側を両方実践されている渡邉先生のような方でないと実感できませんね。私自身、とても貴重な示唆だと感じました。我々がつくばのディープテック・スタートアップを支援している中で、やはりテクノロジーは「要素技術」であることが多いので、その出口としてはメーカー企業などを相手に売り上げを立てることが多くなります。そんなときに、どういう支援があるかと言うと、よく聞かれるのがオープンイノベーションとして大企業とのマッチングイベントです。それはそれで必要なのかもしれませんが、オリエンタル技研工業さんのように主力事業のクライアントと繋がれることは、マッチングイベントよりも信頼性の観点で見れば効果は大きいと思います。この点について、フィコケミー社はANAホールディングス等との業務提携があると思いますが、XiS Worksiteに入居するメリットがあればお聞かせください。
渡邉
先に述べたことを経験に基づき、さらにかみくだいて説明します。大切なことは、新しい要素技術の将来性をしっかりしたモデルをもって評価し、社会実装にむけて本気で取り組んでくれるパートナーとの出会いです。国内だけではそれが難しいことがわかってきましたことから、国際的に広い視野で国際会議や国際誌あるいは自前のワークショップ開催等で新要素技術の内容と将来性を訴え続けています。
私たちが入居しているXiS Worksiteに国内外から訪問した方が、第一印象として共通に発する言葉は、「素敵なところですね」でした。それを聞くと私たちも嬉しくなります。XiS Worksite の会議室を使って、これまで外国の研究チームやビジネスチームとそれぞれ3-4日間ぶっとおしのワークショップを開催しております。オリエンタル技研工業様からはコーヒーの差し入れもあり、アットホームな雰囲気で非常にリラックスして、忌憚のない自由な意見交換ができました。これは堅苦しい技術的・ビジネス的議論のワークショップにもかかわらず、居心地がよかったことを意味し、第一印象とした発せられた言葉が嘘ではなかったことを意味します。さらに、このようなワークショップをもとに、ビジネスチームが開発している技術の将来的発展性の評価モデルにより私たちの新技術を評価してもらいました。評価結果が高かったことから、私たちとビジネスチームの間で新たなパートナーシップ構築の契約の締結の段階まで至っております。XiS Worksiteにはいったことで、やっと本気で取り組んでくれるパートナーに出会うことができました。
屋代
このあたりは、オリエンタル技研工業さんとしても強みとして意識されていますでしょうか?
柄澤
はい。私たちのクライアントさんに「XiS Worksiteにはこんなに面白いスタートアップが入居していますよ」といった話をすると皆さんすごく興味を持ってくれます。すでにいくつかのスタートアップさんとお繋ぎし、色々なコラボレーションがスタートしています。でもまだまだ私たちの発信力が足りていない。もっともっと情報発信し、繋げていきたいと思っています。
屋代
つくば市内にはプロロジスさんの「inno-base TSUKUBA」やアステラス製薬さんの「SakuLab-Tsukuba」など、民間企業が自社施設をスタートアップや研究者に開放して共創を図る動きが出ています。これらの企業は物流、創薬といった自社とのシナジー効果が求められます。とても分かりやすいのですが、オリエンタル技研工業さんとのシナジー効果というと、どういう点があるのでしょうか?

柄澤
ですよね。なぜオリエンタル技研がインキュベーションセンターを?というのはよく言われます(笑)。シナジーはすごくいっぱいあります。わかりやすいところで言うと、新型の実験設備をXiS Worksiteの入居者の皆さんに実際使っていただいてリアルなフィードバックをいただき、製品開発に反映する。また、長期的な視点で考えるとスタートアップさんが将来的に自社の研究施設を持つといった際に施設設計や設備導入といったお仕事に繋げたいといったことがあります。でもこれらの要素は確かにシナジーであるもののそこまで重要じゃない。「ひらめきの瞬間をつくる」と言うのが私たちのパーパスです。日本の科学技術分野をエンタメのように文化にし、科学技術がもっと身近になり、誰もが気軽にサイエンティストになれる社会が実現すれば、日本にはもっとひらめきが生まれて生産性も上がると思っています。XiS Worksiteはそんな未来の実現に向けた私たちの一つのアプローチです。
屋代
ちょっと乱暴ですがオリエンタル技研工業さんは設備屋さんという解釈をすると、スタートアップが成長し、製造拠点を持つようになるとオリエンタル技研工業さんもまた仕事が入るというサイクルで、クライアントの大手企業がスタートアップの技術を買収して事業を大きくすると、ここでも設備投資などで仕事が入るというサイクルは、今の日本にない共創だと思います。そして、この「仕組み」自体をパッケージ化して国内外、特に海外だとグローバルサウスになるかと思いますが、展開できるのではないかとも思っています。それによりスタートアップ支援がさらに厚みを増していく。XiS Worksiteによるオリエンタル技研工業さんの今後の展望をお聞かせください。
柄澤
ありがとうございます。実はすでに候補地をいくつか絞り、次の施設の構想に着手しています。海外も面白いですよね。オリエンタル技研工業では昨年より東南アジアへの進出を進めています。今は研究設備を中心にPRを進めていますが、将来的には「XiSバンコク」なんてのも面白そうです。完全に個人的な思いつき&妄想ですが(笑)。新たな施設展開によるスケールも考えつつ、まずはしっかりここつくばの施設での体験をより充実したものにすることで、本当の意味でのインキュベーションを実行していきたいと思っています。まずは近いうちにBBQやりましょう!
屋代
ありがとうございます。BBQは毎年恒例にしましょう!渡邉さんからもフィコケミーとしての今後の展望をお願いします。
渡邉
大学で藻類バイオマスに関する研究開発を実施しておりましたが、開発した個別技術の社会実装が現実的に動くこととなったことで、大学外にラボを借りることとしました。しかし、既存のレンタルラボは満杯で3年待ちというのが普通で、さらにこちらが要望する450㎡の広さのラボはどこにもありませんでした。つくば市に問い合わせたところ、オリエンタル技研工業様のXiS Worksiteを紹介してくれました。 XiS Worksiteを最初に見学した私たちの印象は確かに「素敵なところ」でした。XiS Worksiteに入って7月1日で2年となりました。この間スタートアップ会社から次のステージへの発展を目指す過程で何とも言えない苦しみが最近まで続きました。しかし、オリエンタル技研工業様の理解とサポートを得て、苦しみを乗り越えてグローバルな事業展開を実施する目途がたってきました。今後は、国内ではANAホールディングス様等のパートナーや国外のパートナーとともに、確かな科学と技術に基づくグローバルなビジネス展開を実施する計画です。
オリエンタル技研工業様の「いくつかのスタートアップ企業と繋いだ色々なコラボレーションを創成していく」(以下共創プラットフォームラボ)という思想には、やっとつくば市でもプラットフォームラボがあらわれたと、感慨深いものがあります。米国では普通に進めているプラットフォームラボ思想であり、国内では川崎市が自ら共創プラットフォームラボを立ち上げ、その運営管理を直接実施しており、そこには敷金はなく、会議室も無料で利用でき、食堂も準備しております。つくば市は大学や研究所が多数集中した国内では類を見ない都市ですので、教員や研究者が開発した技術の社会実装のため、つくば市がスタートアップ企業を設立と育成を促進する「つくば共創プラットフォームラボ」の施設・制度を、オリエンタル技研工業様とともにつくりあげ、発展させていくことを、是非前向きに検討してください。川崎市にできてつくば市ができないことはないと思いますし、それ以上につくば市は、日本の研究学園都市に米国のシリコンバレーのような日本最大のイノベーション拠点を形成できるポテンシャルを持っている都市であることに気づいてください。ただし、イノベーション拠点は大学や研究所の参加・サポートは必要ですが、主役は技術開発企業でないとできません。大企業でプラットフォームラボを作っているところはありますが、基本的には内向きですので、リスク覚悟の強い意志で作られたスタートアップ会社が集まってくる共創プラットフォームラボでなければなりません。つくば市には社会実装可能な技術シーズがたくさん埋もれていますので、是非埋もれているシーズを掘り起こし、スタートアップの舞台にたたせ、その育成と発展をサポートする「つくば共創プラットフォームラボ」構想を実現させてください。その実現はつくば市の大きなサポートがないとできないものであり、そのためには私たちも協力・サポートを惜しむものではありません。
屋代
ありがとうございます。そのご期待に応えられるよう、そしてつくばがスタートアップ・エコシステムの拠点として成長できるよう、常に視野を広く持ち、前例に捕らわれない組み合わせを模索していきたいと思います!
本日はどうもありがとうございました!
柄澤
渡邉
ありがとうございました!
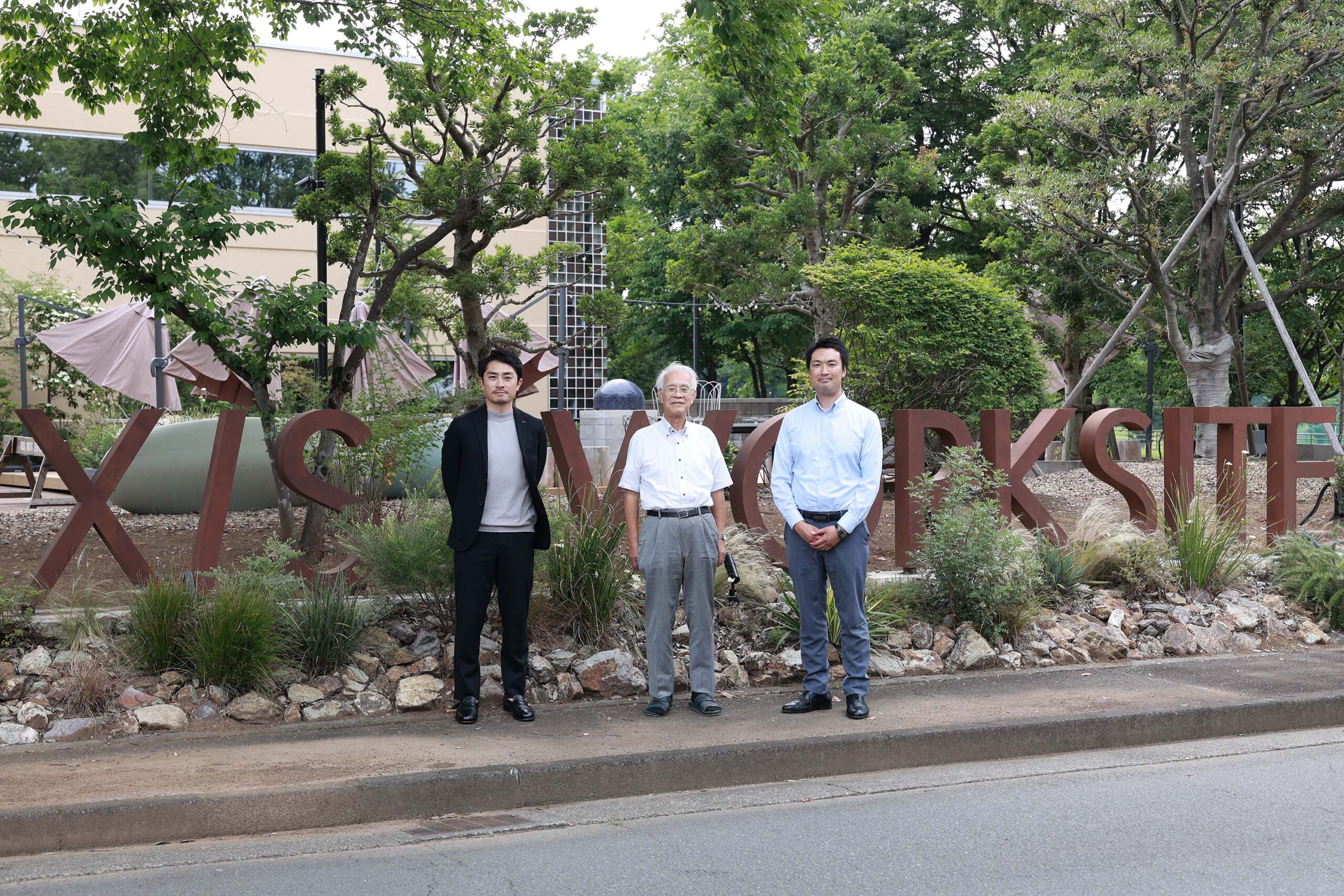
経済学者J.A.シュンペーターの造語である「Innovation」は「新結合」と訳されています。そして、イノベーションはゼロからイチを作り出すことではなく、5つの要素の新結合の実行です。その新結合において、「ひらめき(A Bright Idea)」も重要な要素となり得ます。
基礎研究から社会実装を経てスケール化し、人々の暮らしをより良いものに変えていくイノベーション。これらは産業界によるラボ施設などのハード面と人を繋いでいくソフト面での支援と「企業家」の前進するパワーが融合することで大きなものへと成長していきます。
スタートアップが挑戦し、成長し、世界へ飛び立つ旅の物語
“つくばスタートアップジャーニー”
未来のための、あなたの旅の仲間はここにいます。

柄澤さん、渡邉さん、よろしくお願いします!