越境する知。国環研発ベンチャー第1号、その社会実装への挑戦
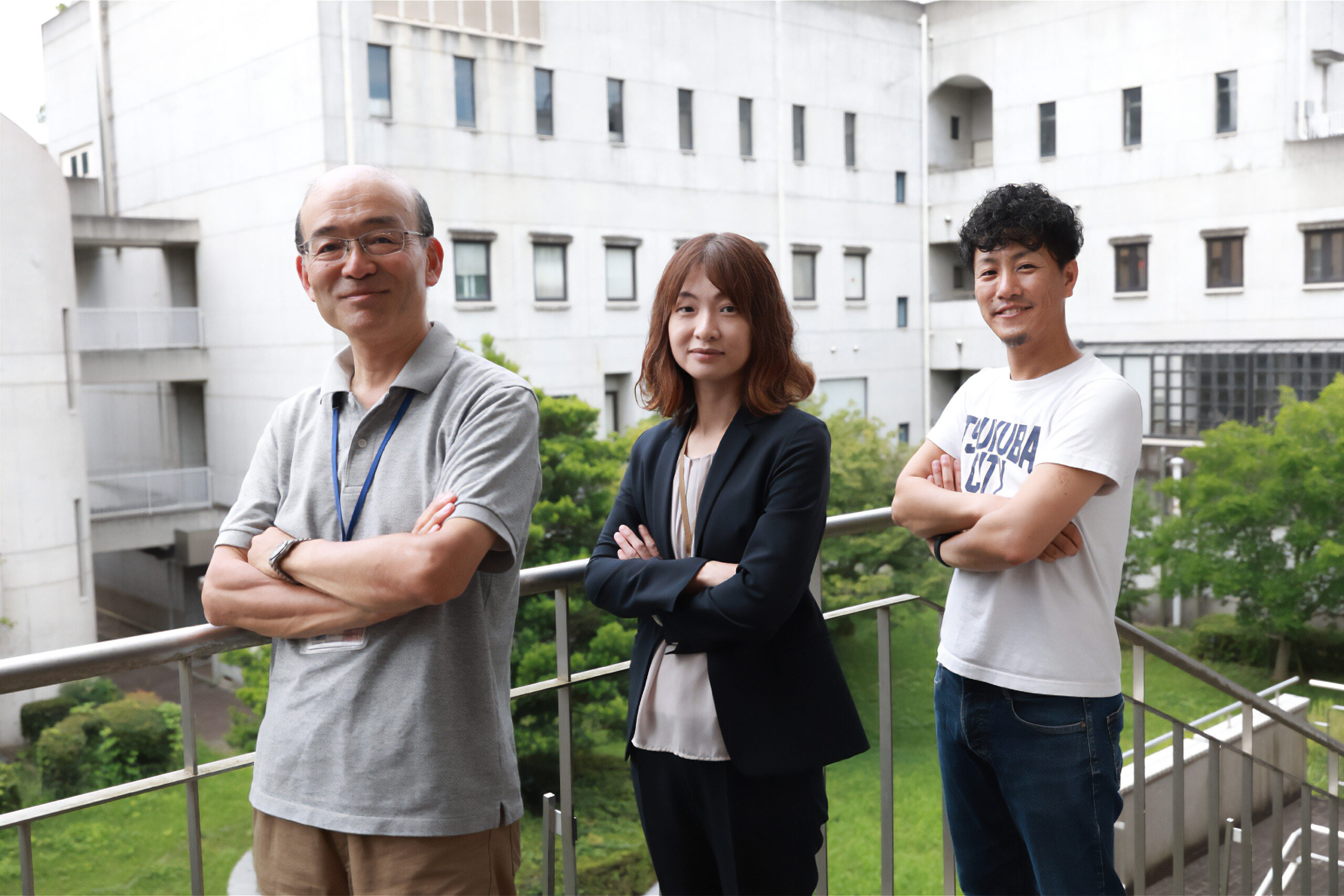
国立研究開発法人国立環境研究所 連携推進部 研究連携・支援室 室長山口 晴代(やまぐち はるよ)
筑波大学大学院生命環境科学研究科にて博士号を取得。その後、国立研究開発法人国立環境研究所にて環境問題の原因となる微細藻類に関する研究をしている。2021年からは、研究者の内部出向で、連携推進部にて、ベンチャー支援、共同研究契約、知的財産の管理の業務を行っている。
株式会社野生動物医科学ラボラトリー 代表取締役大沼 学(おおぬま まなぶ)
国立研究開発法人国立環境研究所・生物多様性領域・生物多様性資源保全研究推進室室長。1993年3月酪農学園大学酪農学部獣医学科卒業(獣医師)。斜里町役場、青年海外協力隊(マレーシア)を経て、2003年3月北海道大学大学院獣医学研究科修了(博士(獣医学))。大学院終了後に京都大学霊長類研究所を経て、2004年4月より国立環境研究所に勤務。国内および東南アジア地域で絶滅危惧種の遺伝学的研究、繁殖学的研究、遺伝資源保存を実施してきた。また,野鳥の鳥インフルエンザウイルスの保有状況調査やイノシシを対象とする豚熱の調査を担当してきた。2024年10月株式会社野生動物医科学ラボラトリー設立。
株式会社しびっくぱわー 代表取締役社長堀下 恭平(ほりした きょうへい)
1990年熊本市生まれつくば市在住。東日本大震災を機に筑波大学2年次にコミュニティカフェを創設運営。下妻市や水戸市、横浜市などの商店街活性化に参画した後、行政計画策定支援で最初の起業し以降8社起業経営参画。全国60自治体以上の総合計画や総合戦略などの行政計画を策定。まちづくりとスタートアップ支援を中心に年間1,500件以上のイベント企画運営登壇。2016年あらゆる挑戦を応援する場Tsukuba Place Lab創業、2021年つくばスタートアップパーク運営、2024年常陸多賀駅前 晴耕雨読を事業承継し経営。令和元年度茨城県知事表彰 新しいいばらきづくり表彰 産業振興 受賞。
聞き手:株式会社しびっくぱわー 代表取締役社長 堀下恭平
※本インタビューでは、スタートアップとベンチャーを同義語として扱います
筑波研究学園都市には、我が国の科学技術を牽引する多様な研究機関が集積し、それぞれが専門性の深化と社会との接続を模索しています。国立研究開発法人国立環境研究所(以下、国環研)もその一つ。近年では、環境研究の成果を社会へと還元する新たな手段として、スタートアップ支援の枠組み構築に取り組んでいます。
その第一歩として、国環研から初めて誕生した認定ベンチャーが「株式会社野生動物医科学ラボラトリー」です。研究成果の社会実装を目指し、獣医師であり研究者でもある大沼学さんが立ち上げたこの会社は、「野生動物」という専門的かつ社会性の高い領域において、研究機関と現場の橋渡しを担っています。
今回は、国環研において制度設計と支援の中核を担った山口晴代さんと、起業家としてその道を選んだ大沼学さんのお二人にお話を伺い、制度の壁を越えた“越境する知”の背景と、研究機関発ベンチャーの可能性に迫ります。
01. 制度の枠を越えて、初の挑戦に踏み出す
堀下
山口
大沼
よろしくお願いします。
堀下
今回は“国環研発ベンチャー第1号”立ち上げ秘話を伺いたいと思います。
まず、山口さん、この制度づくりはどう始まったんでしょうか?
山口
2021年に連携推進部へ異動した際、ちょうど研究成果の社会実装が大きなテーマになっていて。「国環研として、研究を社会にどう還元するか?」という問いが投げかけられていたんです。その中で、私は“起業”という社会実装の形に注目し、「それを後押しする仕組みを作りたい」と思うようになりました。けれど、当時はベンチャー支援の制度も、前例も、なにもない状態。だから、ゼロからの制度設計に挑むことになりました。
堀下
仕組みそのものを自分たちで作っていくというのは、相当大変だったのでは?
山口
はい、毎日が挑戦でした。でもその分、やりがいも大きかったです。研究所の中に前例がない分、ひとつひとつを手探りで確認しながら進めました。たとえば、どんな支援項目が必要か、どこまで所内リソースを使っていいのか、契約書の形式や審査のフローはどうするのか……全部が“初めて”の連続で。
それでも、丁寧に一歩ずつ積み上げていけば、形になっていく実感があって。制度設計って、ややもすると堅苦しい作業に思われがちですが、私はむしろ“創造的なプロセス”だったと思っています。どこまでが安全かを考えながらも、挑戦の芽を潰さないようにする。そのバランス感覚をすごく鍛えられましたね。
堀下
まさに“制度の枠を越える”という表現がぴったりですね。そして、そんな制度に最初に手を挙げたのが大沼さんだったと。
大沼
山口さんには悪いのですが、正直に言うと、研究所にこのような支援制度があることを知りませんでした。ですが、この支援制度の詳細を山口さんを通して知り、「じゃあやってみよう」と決意しました。研究者としても獣医師としても、現場にもっと近いかたちで社会と関わりたいと思っていたので。
山口
最初の挑戦者が現れた瞬間、本当に嬉しかったです。制度って、つくっただけでは意味がないんですよね。誰かが実際にその制度を使ってくれることで初めて“命が吹き込まれる”。大沼さんが名乗りを上げてくれたからこそ、この制度は制度として機能しはじめた。今振り返っても、あれは“越境”の瞬間だったと思います。

02. “診る”を届けるために、研究者が起業を選んだ
堀下
大沼さん、研究者から起業という、なかなか踏み出せない一歩を選んだ動機に、野生動物医療というテーマの特性が大きく関与していると感じます。
大沼
そうですね。野生動物医療という分野は確かにニッチです。でも、社会性が非常に高いんです。たとえば、鳥インフルエンザのような感染症の拡大といった危機は、野生動物だけでなく私たち人間にも深刻な影響をもたらします。国環研で開発した病原性判定技術は、従来10日ほどかかった判定を3日、さらに1日で可能にする画期的なものなんです。これにより、感染拡大への迅速な対応や防疫対策の立案が可能になりました。
堀下
その背景には行政や研究機関では動きにくい現場へのスピード感のジレンマがある、と
大沼
まさに。私は知床国立公園を皮切りに、沖縄やマレーシアなど国内外で野生動物の保全に関わる研究に従事してきました。その中で、様々な形の組織を自ら立ち上げ保全に携わる方々に接し、自分でもいつか“器”を整え、保全に関わりたいと思っていました。
堀下
会社という形は、自由度と専門性双方を実現する手段だったのですね。
大沼
はい。「株式会社野生動物医科学ラボラトリー」は、野生動物の疾病に関する検査をすることで、野生動物の生息地でどのようなことが起こっているのかということを考える視点も大切にする存在でありたいと考えています。現場で得たデータを科学分析し、その成果を公衆衛生や保全政策に還元する。その両輪がなければ、この分野の社会実装は進みにくいと思ったんです。
堀下
挑戦の道には、多くの困難も伴ったのでは?
大沼
もちろんです。資金調達、制度統合、所内の理解促進など、課題は山積でした。しかし、国環研の山口さんをはじめ、一緒に制度の整備を進めてくれた方々に支えられたことで、事業を形にできた。この起業において支援体制がいかに重要かを痛感しました。
山口
大沼さんのお話には誠意と情熱が込められていました。だからこそ支援側も真剣に向き合い、伴走できた。支援制度が挑戦に応えた事例として、私たちにとって貴重な経験になりました。
堀下
診療と研究をつなぎ、社会への実装を目指す大沼さんの起業のストーリーには、人の命と知の広がりが見えますね。

03. 国環研発ベンチャーが示す、新たな“知のかたち”
堀下
起業した後、ご自身や国環研の空気に変化を感じる場面はありましたか?
大沼
大きかったですね。起業する前は、研究成果を実際に社会で活かす、いわゆる「社会実装」という言葉を実感がないまま使っていたように思います。今では、以前よりも研究成果を実際に社会の中で活かしたいと気持ちが強くなりましたし、「社会実装」を実践しているという感覚があります。
堀下
研究者としての視座が、社会の現場とより結びついたわけですね。
大沼
はい。あと、国環研の中でもこの取り組みに対する空気が少し変わったように感じます。最初は本当にできるの?という戸惑いもあったと思いますが、今は応援の声も増えてきていて、挑戦を肯定的に捉えるムードが少しずつ広がっている印象です。
山口
その空気の変化は、確実にありますね。ベンチャー支援制度ができたことで、他の研究者の方からも実はこういうことをやってみたいと思っていたという声が届くようになりました。制度って、誰かが使ってくれたことで初めて説得力を持つんです。
堀下
なるほど。まさに、大沼さんの一歩が制度の説得力になったと。
山口
ええ。そして、この制度が今後どう広がっていくかを考えたときに、制度×個人の意思×社会的ニーズという三つの掛け算が大事だと思っています。制度はあくまで下地であって、そこに個人の熱意や実現したいビジョン、そして社会の求める声が重なって初めて、動き出す。
堀下
越境する知というテーマに重ねると、制度や専門性という内にあるものが、社会という外とどうつながるかがカギになってきますね。
山口
まさに。国環研はこれまで、国内外の学術的成果を重ねてきましたが、それらをどう社会に届けていくかがこれからの課題です。その意味でも、大沼さんのように制度を越えて動いた人の存在は非常に象徴的です。
大沼
自分の起業が、そういうふうに捉えてもらえるのは嬉しいですね。でも、本当にまだまだこれからです。次に続く人たちのためにも、自分自身がまずしっかりと成果を出していきたいと思っています。
堀下
大沼さん、山口さん、今日は本当にありがとうございました。お二人の話から、研究機関の中にある知が、制度と社会を越えて動き出す瞬間を感じました。次なる挑戦者の登場にも、今から期待が膨らみます。

新しい挑戦には、常に困難がつきものです。
それでもなお一歩を踏み出すのは、想像力の翼が、既存の境界を超えて“まだ見ぬ可能性”を信じているからに他なりません。
野生動物という複雑で繊細な領域において、研究者が起業という手段を選び、制度の壁を乗り越えながら社会とつながる道を切り拓く——。それは、知の現場が持つ力を社会の最前線へと届ける、まさに「越境する知」の実践にほかなりません。
研究と社会、制度と個人、理想と現実。そのあいだをつなぎ、進み続ける勇気が、未来を形づくっていきます。
スタートアップが挑戦し、成長し、世界へ飛び立つ旅の物語
“つくばスタートアップジャーニー”
未来のための、あなたの旅の仲間はここにいます。

山口さん、大沼さん、よろしくお願いいたします。